虹って、どうしてあんなにきれいなアーチ(弧)に見えるのでしょう?
じつは、太陽の光と空気中の水滴がつくる、規則正しい“角度”の結果なんです。
太陽の光が水滴に入ると屈折(くっせつ)して(水の中で光の進む向きが変わる)、中で反射し、もう一度屈折して外に出てきます。
このとき、ちょうど42度くらいの角度で出てくる光だけが、私たちの目に届くようになっています。

へぇ〜!虹って“なんとなく”できるんじゃなくて、ちゃんとルールがあるんだ!

その通りです。太陽を背にして空を見ると、42度の位置に光が集まって、色の帯ができる。だからアーチになるですよ。
この角度で見える光が集まった形が、あの大きなアーチなんです。
しかも、実は虹の形は本当は丸いんですよ。地面があるから上半分だけが見えているんです。
今回は、この「虹がアーチになる理由」を、やさしく分かりやすく解説していきます!
虹がアーチに見えるのはなぜ?
虹がアーチに見える理由は、光と水滴と太陽の位置関係にあります。
太陽の光が水のつぶに入って反射すると、決まった方向に光が出てきます。
この方向は、太陽を背にして空を見ると、目から見ておよそ42度の角度になります。
この42度の方向にそって、色のついた光が空に並ぶと、虹のアーチ(弧)が見えるというわけです。

虹って、太陽の反対側に出るのもちゃんと理由があったんだね!

はい。光の動きと角度によって、決まった場所に現れるんです。
虹の形は「アーチ」じゃなくて「まる」だった!
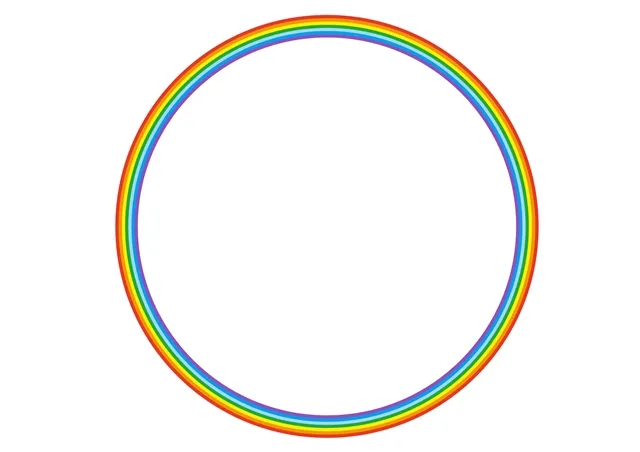
実は、虹の本当の形はアーチではなく円です。
私たちが地上から見ると、地面にさえぎられて上半分しか見えないため、アーチのように見えるのです。
でも、もし飛行機の中や高い山の上など、地面が視界に入らない場所から見れば、虹がまんまるの輪として現れることもあります。

えっ!? 虹って本当は輪っかなんだ!

そうなんです。虹の中心は“対日点”といって、太陽と反対方向にあります。
つまり、虹がアーチ状に見えるのは、地面があるから上半分だけが見えているというだけのこと。
光と太陽と水滴の関係によってできる虹の本当の形は、空に描かれた大きなまんまるだったのです。
なぜ虹は42度で見えるの?色はどうして七色なの?
光は曲がって反射して、また曲がる
太陽の光が水滴の中に入ると、曲がります(屈折)。
そのあと水滴の内側で反射して、もう一度曲がって外に出てきます。
この「屈折 → 反射 → 屈折」の動きによって、光は42度くらいの角度で外に出てきやすくなるのです。
色によって角度が少しちがう
実は、光の色によって曲がり方は少しずつちがいます。
たとえば:
- 赤い光:あまり曲がらない → 外側に見える
- 青や紫の光:よく曲がる → 内側に見える
この違いによって、虹では赤が外側、紫が内側という順番になるのです。

じゃあ、あの並びもちゃんと“物理のルール”でできてるんだね!

ええ。太陽の光がいろんな色をふくんでいる証拠なんですよ。
なぜ「七色」と言われるの?
実際の虹には、七色よりもたくさんの色がふくまれていますが、日本では七色で教えられることが多いです。
これは、光を7つに分けたと言われるアイザック・ニュートンの影響もあるとされています。
二重虹(ダブルレインボー)のひみつ

ときどき、虹が2本見えることがあります。
これを「二重虹(ダブルレインボー)」と呼びます。
しかも、よく見ると2本目の虹の色が反対になっているのです!
水滴の中で2回反射してできる
ふつうの虹は、水滴の中で1回反射した光が見えてできています。
でも、二重虹では2回反射した光が目に届くのです。
この2回反射のとき、光はちがう角度(だいたい50〜53度)で出てきます。
そのため、2本目の虹は、最初の虹よりも外側に、そして少しぼんやりと現れるのです。

うわぁ〜!2本の虹ってめったに見られないよね!

はい。しかも、2本目の虹は色の順番が逆になります。赤が内側、紫が外側にくるのです。
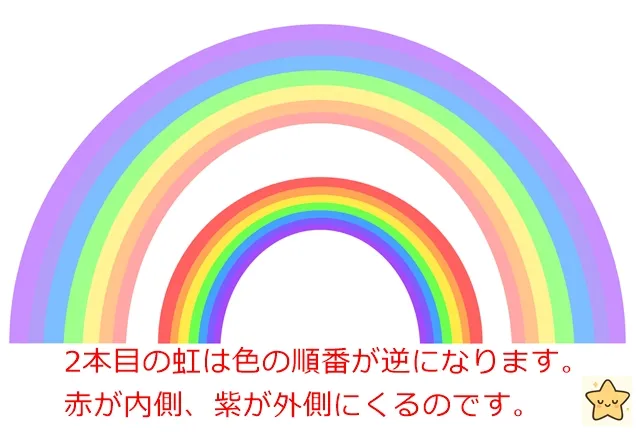
なぜ色が逆になるの?
それは、光が水滴の中を2回反射すると、出てくる向きがひっくり返るためです。
その結果、虹の色の並びも反対(逆順)になるのです。
二重虹が見られるのはレアなチャンス!
2回反射した光はとても弱いため、二重虹はふだんはあまり見られません。
でも、雨上がりの明るい空や、条件がそろった日には見られることもあります。
もし2本目の虹を見つけたら、ちょっといいことがあるかもしれませんね!
虹が見える条件とは?
虹は、いつでもどこでも見られるわけではありません。
実は、虹が見えるためには、いくつかの条件がそろう必要があります。
- 太陽が出ている(できれば朝や夕方)
- 空気中に水滴がある(雨・霧・噴水など)
- 太陽を背にして、反対側の空を見る
この3つがそろったとき、空にきれいな虹が現れるチャンスです!
① 太陽の光が必要
まず、一番大切なのは太陽が出ていることです。
太陽の光がなければ、そもそも虹はできません。
とくに太陽の位置が低い朝や夕方の方が、虹が見えやすいです。
② 空気中に水のつぶがある
虹をつくるもうひとつの材料が、空気中の水滴(すいてき)です。
この水滴は、雨あがりの空や霧、噴水、滝、ホースのしぶきなどで見られます。
③ 太陽を背にして空を見る
虹を見つけるには、太陽を背中にして、反対側の空を見てみましょう。
なぜなら、虹は「太陽の光が水滴で反射して戻ってくる方向」に現れるからです。

雨がやんだあとに虹が出るのって、太陽と水がそろうからなんだね!

はい。その通りです。太陽の光が後ろから差し込み、水滴の中で反射・屈折して、あなたの目に届くと、虹が見えるのです。
観察してみよう!虹をもっと楽しむポイント
虹のしくみが分かったら、今度は自分の目で観察してみましょう!
① 太陽の位置と向きをチェックしよう
虹は太陽を背にして、その反対側にある空に現れます。
朝や夕方など、太陽が低い時間帯の方が、虹は高く・大きく見える傾向があります。

朝の虹って、なんだか空にかかる橋みたいでかっこいいよね!

はい。時間帯や見る場所によって、虹の高さや明るさも変わるのですよ。
② 自分で虹を作ってみよう!
晴れた日に、太陽を背にして水をまくと、人工的に虹を作ることができます。
たとえばこんな方法があります:
- 庭や公園で、ホースの霧をまく
- 霧吹きで細かい水を空中にまく
- シャボン玉やスプリンクラーでもOK!
条件がそろえば、七色の小さな虹が見えるはずです。
③ 虹を撮影するときのコツ
虹を写真に残したいときは、順光(太陽を背にする)で撮ることと、ピントを空の奥に合わせるのがポイントです。
二重虹などは、少し暗めに撮ると色がくっきり写ることもあります。
④ 雨上がりには空を見上げてみよう!
虹が出やすいのは、雨のあとの晴れ間や、天気雨のとき。
とくに西の空が晴れていて、東の空に雨が残っているときなどは、虹が見えるチャンスです。
まとめ:虹のアーチにはちゃんと理由があった!
虹がアーチになるのは、偶然ではありません。
実はすべて、太陽の光と水のつぶが作る“決まった角度”の現象だったのです。
この記事でわかったこと
- 虹は、光が水滴の中で屈折→反射→屈折することでできる
- そのとき42度の角度で出てくる光が集まり、アーチの形になる
- 虹は本当は円形で、地面があるからアーチに見える
- 光の色は曲がり方がちがうので、七色に分かれて順番に並ぶ
- 水滴の中で2回反射すると、2本目の虹(二重虹)ができ、色が反対になる
ちょっとした自然現象の中にも、物理や光のふしぎがたくさんつまっています。
ぜひ空を見上げて、今日も「科学の目」で自然を楽しんでみてくださいね!


